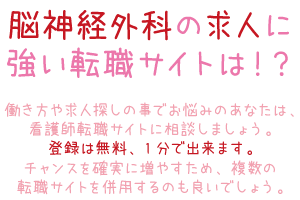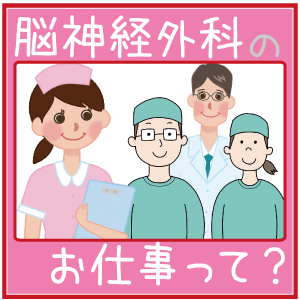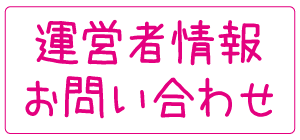当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています

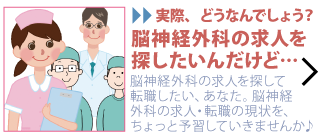
脳神経外科の看護師の勉強というと「専門的で難しそう」というイメージは無いでしょうか。
でも、ポイントを押さえて勉強すれば、他の分野に比べて特別難しいということはありません。
ここでは、私が脳神経外科の看護師として働いていて感じた、勉強しておいたほうが良いポイントを紹介します。
目次 [目次を隠す]
脳神経外科の看護師の勉強ポイント・・・①解剖生理をマスターすることで病気の理解につながる

脳神経外科の看護師として働くにあたり、避けられないのが脳の解剖生理です。
脳の構造や血管、それぞれの部位の果たす役割を覚えることが大切です。
でも、脳神経外科の勉強に苦手意識があると、この時点で「私には無理」と思ってしまいがちです。
実際に私も、看護学生の頃は脳の勉強が苦手でした。
「脳神経外科の看護には興味があるけど、勉強は苦手だからどうしよう。」とずっと思っていました。
もしかしたら以前の私みたいに、覚える量が多いと難しく感じてしまう人もいるかも知れませんが、一度覚えてしまうと色々な病気の理解につながるので、簡単な面もあります。
例えば「脳幹出血」の患者さんがいたとします。脳幹とは呼吸や体温中枢・心臓の働きなどを調節しており、人間が生命を維持するのに非常に重要な役割を担っている部分です。
その脳幹が出血を起こすということは、それらの役割が果たせなくなるので、呼吸障害が起こったり高熱にさらされたりします。
このように解剖生理を理解していると、病名を聞いただけで起こりうる症状の予測がつきます。
脳神経外科の看護師の勉強ポイント・・・②麻痺のある患者さんの介助方法

脳神経外科では麻痺のある患者さんが多いです。
そこで、脳神経外科の看護師の勉強においても、麻痺のある患者さんに対する介助は必要になります。
特に、食事・移動(歩行介助・車いすへの移乗介助)・更衣の介助方法は必ず勉強した方が良いです。
正しい介助方法ですることは、事故の防止だけでなく、患者さん自身も楽に介助を受けることができます。
また、患者さんが自立に向かうように支援するためには、看護師自身が方法を理解している必要があります。
ただ「麻痺のある患者さんの介助」といっても、麻痺の程度によっても介助方法が変わってくることがあります。
私も働いていく中で、先輩の看護師に教わりながら理解を深めていきました。
もしあなたが「患者さんにケガをさせてしまいそうで怖い」という思いで、脳神経外科の看護師を躊躇しているのなら、働きながらも学べる場が多いので、不安に思いすぎず、先輩の看護師にどんどん相談しながら習得していくと良いと思います。
脳神経外科の看護師の勉強ポイント・・・③失語や呂律障害のある患者さんとのコミュニケーション方法
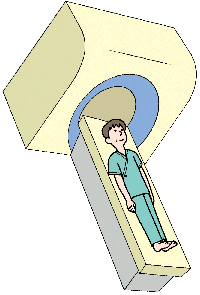
脳神経外科では、脳の障害が起こっている部位や大きさによっては、失語症や呂律障害のある患者さんがいます。
言語的コミュニケーションがスムーズに図れないことは、患者さんにとって大きなストレスとなります。
「痛い」「吐きそう」といった症状を訴えることさえも難しいことがあります。
そこで、脳神経外科の看護師はジェスチャーやイラストを用いたり、患者さんが応えやすいような質問の仕方をしたり、呂律障害においては口の運動を促したりといったことが必要になります。
言語の障害といっても、失語症と呂律障害では原因やコミュニケーション方法が異なる部分があるので、しっかり区別して理解しておいた方が良いです。
ここまで脳神経外科の看護師の勉強ポイントを3つご紹介してきましたが、いかがでしょうか。
教科書や参考書だけでは、難しくて十分に理解できないこともあるかと思います。
もし、あなたが脳神経外科の看護師に興味を持っているのなら、一度見学をしてみるのも良いと思います。
病院によっては、看護師の知識がアップするように勉強会をしているところも多いです。
ひとりで病院の情報を集めたり、見学の調整をするのは大変なので、そういうときは看護師専門の転職サイトに登録することをオススメします。
必ずあなたの力になってくれると思います。

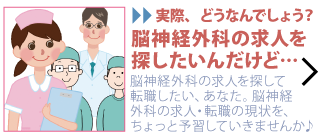
執筆者情報
 脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ! 編集部
脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ! 編集部
脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ!は、厚生労働大臣から転職サポート(有料職業紹介事業)の許可を受けた(許可番号13-ユ-314851)株式会社ドリームウェイが運営するメディアです。転職サポートの経験を活かし、定期的なリライトや専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。