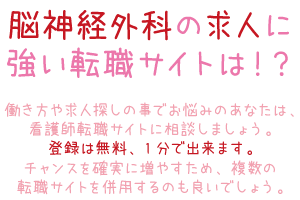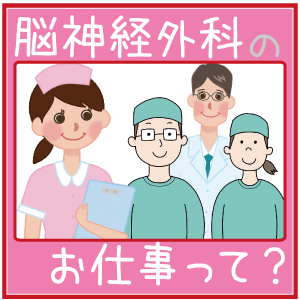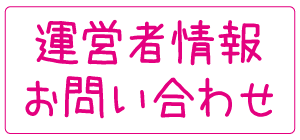当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています

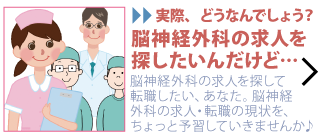
脳神経外科の看護師が知識として知っておいたほうが良いことはたくさんあります。
勉強に関する知識は「勉強」のコラムを見てもらうと参考になるかと思います。
ここでは、脳神経外科の看護師として働く上で知っておいた方が良いミニ知識や、病棟の特性ごとの必要な知識の違いなどを紹介したいと思います。
脳神経外科の看護師の知識・・・略語系

私が脳神経外科に配属されることが決まってから、参考書などで自分なりに勉強していました。
でも、実際に働き始めて、初めて申し送りを聞いたときには頭の中が「?」「?」「?」だらけになりました。
聞いたことのないような略語がたくさん飛び交っていたからです。
分からない略語をメモして調べたり、調べても分からないことは先輩に聞いて意味が分かると「なんだそんなことか。略さずに普通に言ってくれたら分かるのに!」とよく思っていました。
知っている言葉なのに、略語が分からないために意味が理解できないのは勿体ないですよね。そして何より困ります。
私は、看護師向けの略語本を一冊買いました。脳神経外科特有の略語を集めた本もあります。
ナース服のポケットに入るぐらいの小さいサイズのものだと、分からないときにサッと取り出して調べることができてとっても便利でした。
先生が書くカルテも、脳の血管名や病名などは英語や略したスペルが書かれているので、カルテを読むときにも役に立ちます。
脳神経外科の看護師の知識・・・病棟の特性ごとの必要な知識

SCU(脳卒中ケアユニット)を立ち上げているような病院では、発症直後の重症な患者さんが救急車から運ばれてきたり厳重な管理下での治療が必要な患者さんばかりなので、より専門的で高度な知識が必要になります。
ICU(集中治療室)の脳バージョンと思ってもらえるとイメージしやすいかも知れません。
心電図モニター、輸液ポンプ・シリンジポンプなどのME機器はもちろんのこと、人工呼吸器・Aライン・ICPモニター・ドレーン管理の知識が必要になります。
t-PAの治療や看護の勉強も必要です。
脳神経外科の中でも、急性期~リハビリ期をメインにしている病棟では、病気に関する知識以外にも退院支援に関する知識が必要になります。
介護保険の申請に関することや、リハビリ病院への転院は発症後何日までなら可能なのかといったことを理解して置かないと、患者さんや家族に、適した時期での説明や介入ができなくなります。
脳出血の患者さんなど、退院後も血圧管理が必要な場合には生活指導も重要になります。
再出血を起こして再入院になる患者さんも多いので、血圧の変動に注意した生活の仕方など、指導できる知識が必要です。
また、脳神経外科のリハビリ期に起こりやすい合併症のひとつに、誤嚥性肺炎があります。
通常、食べ物や飲み物が気管に入ると咽るので、「誤嚥しているかも!」と気が付きやすいです。
でも、病気により嚥下反射が低下していると、ムセはなくパクパク食事も取れているのに実は誤嚥していたということもあります。
「ムセが無い=ちゃんと食べれている」のではなく、嚥下障害のある患者さんの食事形態が変わった時には特に注意して飲み込み状態や呼吸音、痰の増加や発熱はないかなどを見ていく必要があります。
脳神経外科の看護師の知識・・・どうやって身に付ける?
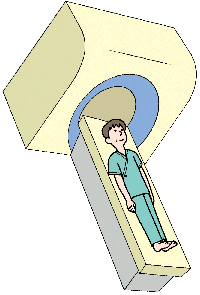
「脳神経外科の看護師として必要な知識は分かったけど、じゃあどうやって身に付けたら良いの?」
「私が興味を持っている脳神経外科ではどのような知識が必要なの?」
ひとりで座学で勉強するには限界があると思います。実際に働き出すと、事前に勉強したつもりでもいろいろ分からないところが出てくると思います。
疑問はそのままにせず、その都度解決していくことで、あなたの知識も自然と増えていきます。
脳神経外科に関する研修やセミナーに参加するのも良いと思います。
転職サイトに登録すると、その病院の脳神経外科の特性(SCUはあるのか、急性期かリハビリ期か、手術の件数は多いか)などの情報がたくさんあるので、どういった知識が必要なのかも分かってくると思います。
逆に、自分の今までの知識や経験を活かした病院を探すことも出来ます。まずは一度転職サイトに登録してみるのも良いと思います。

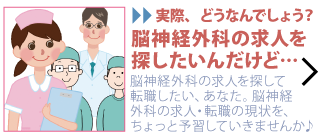
執筆者情報
 脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ! 編集部
脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ! 編集部
脳神経外科の看護師 求人を探している人、この指とまれ!は、厚生労働大臣から転職サポート(有料職業紹介事業)の許可を受けた(許可番号13-ユ-314851)株式会社ドリームウェイが運営するメディアです。転職サポートの経験を活かし、定期的なリライトや専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。